「あとちょっと待ってね」
保育の中で、子どもたちにこんな言葉をかける場面はあると思います。トイレの順番を待つとき、食事を配膳しているとき、お散歩に出発する前の準備中など、「待つ」という行為は、日常の中にたくさん存在します。
子どもたちにとって、時間の感覚はまだ曖昧であり「待つことそのもの」が大きなストレスになる場合があります。ただし、保育の工夫をすることで待つ時間を“ただの我慢”ではなく、“楽しいひととき”や“学びの時間”に変えていくことができます。
待つことは我慢だけじゃない
待つことが学びにつながる場合もあります。例えば、以下のような例です。
- 相手のペースを尊重することを学ぶ
- 自分の気持ちをコントロールする練習になる
- 集団生活でのルールや秩序を感じ取る
しかし、「ただ静かに待ってね」と伝えても、子どもの視点になってみると、すぐに動きたくなる、声を出したくなるのは自然なこと。「待てない=困ったこと」と捉えるのではなく、「成長の途中」と捉えることが、まずは大切な視点ではないでしょうか。
楽しく待てる工夫を考えてみよう
ここからは、楽しく待てるアイデアを紹介します。
ちょっとした遊びを取り入れる
「せーの!」で手をたたくリズム遊びや、保育者が出すポーズをまねっこするゲーム。ほんの数分でも場が和み、待ち時間が楽しいものに変わります。
歌や手遊びで雰囲気を和やかに
おなじみの童謡や手遊び歌は、みんなで一体感を持ちながら待つ時間を過ごせる定番の方法です。「順番が来るまでこの歌を歌おうね」と声をかければ、子どもも見通しを持ちやすくなります。
待つ時間に役割を持つ
「次のお友だちに教えてあげてね」「カゴを持ってくれる?」など、ちょっとしたお手伝いをお願いすると、子どもたちは“待つ人”から“役割を持つ人”へと気持ちが切り替わります。
見通しを伝える
「あと3人でおしまいだよ」「先生が歌を歌い終わったら行こうね」と伝えるだけでも、子どもは「どのくらい待てばいいのか」を理解でき、安心して過ごせます。
「待つ時間」も育ちの一部
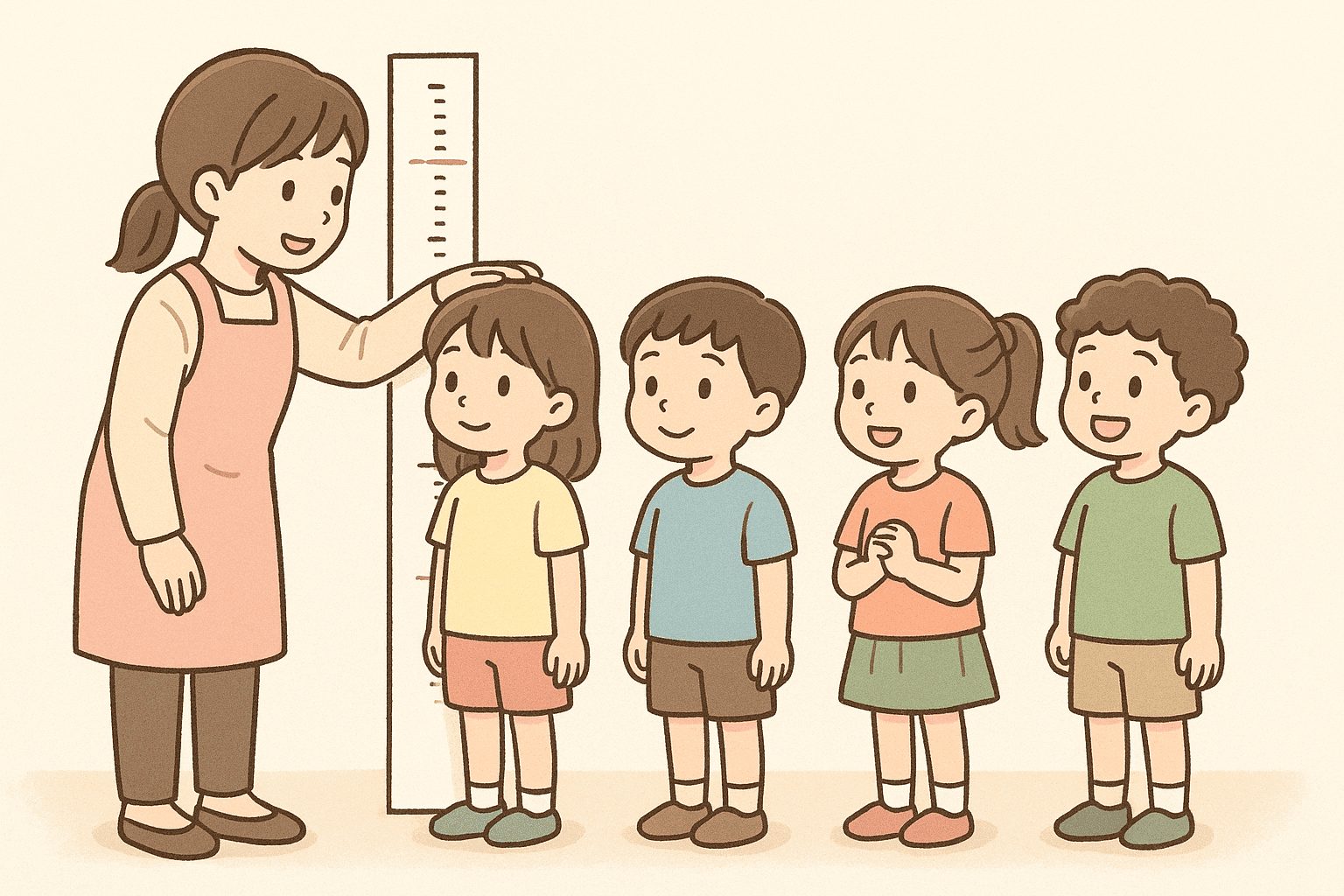
待つという経験は、ただの「退屈な時間」ではありません。保育者が少し工夫して声をかけたり、遊びの要素を取り入れたりすることで、子どもたちは人を思いやる気持ちや、自分の順番を待つ力を自然と育んでいきます。
待つ時間の過ごし方を、発達や個々の興味と照らし合わせながら考えていきましょう。
 |
佐藤愛美(さとうめぐみ)
保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。 保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。 |
