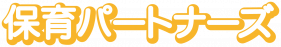日本は世界的に見ても地震が多い国です。2011〜2020年までに世界で発生したマグニチュード6.0以上の地震のうち17.9%は日本周辺で発生していることが分かっています。(※参考)
2011年に発生した東日本大震災は、地震発生後に大津波が押し寄せたこともあり、関東・東北地方に甚大な被害をもたらしました。そして、被災地の保育園や学校では子どもや職員も犠牲になってしまいました。
過去の震災の経験を活かし、保育中の地震に備えるにはどうしたらよいでしょうか。子どもたち、そして自分たちの命を守るために大切な情報をまとめました。
※参考
地震発生後、保育士がやるべきことは?
⒈避難誘導
地震が発生したら、子どもたちを空間の中央に集めます。保育者は防災ヘルメットをかぶり、近くにマットや布団、防災頭巾などがあれば子どもたちに被せて頭を守ります。机などがあれば潜るように指示を出しましょう。
パニックになりやすい子がいる場合は近くにいき、揺れがおさまるまでは隣にいましょう。(パニックになり転倒したり、揺れが止んだ直後に部屋を飛び出してしまう子もいます)
地震の揺れがおさまったら安全な場所に避難誘導します。非常用持ち出し袋が取り出せる場合は持っていきます。責任者から指示があればそれに従い、指示がない場合は避難訓練で定められたルートを通って安全な場所まで移動します。乳児の場合はできるだけ抱っこ紐やおんぶ紐を使用し、保育者の両手があくようにしましょう。
避難経路であっても火災の発生やガラス破片の散乱などのリスクがあるので注意してください。
⒉人数確認
安全な場所に移動したら、人数確認をします。目視だけでなく、2人以上で点呼をし、結果を責任者に報告します。もしも行方不明の子どもがいる場合、すぐに責任者や他の保育士にも共有します。建物の崩壊や津波の危険性がある場合はむやみに探し歩かず、救助隊を待ちましょう。
⒊応急救護
怪我をしている子どもや職員がいる場合、応急手当が必要です。軽い出血や切り傷であれば自分たちで対応できますが、心肺停止や大量出血など深刻な状態の場合はすぐに119番をして救急車を呼びましょう。震災時はすぐに救急隊が駆けつけられない可能性もあります。状況に応じた応急処置の方法やAEDの使い方を日頃から学んでおくことが大切です。
⒋周囲の安全確認
余震が落ち着いたら園の敷地内や周辺の安全確認をしましょう。倒れそうな木や電柱、傾いた建物、地割れはないか、ガラスの破片が散らばっていないか、屋根瓦や外壁などが壊れていないかなどを確かめ、危険な場所にみんなが近寄らないように情報共有を行います。
地震後に火災や津波が発生する可能性もあるので、十分に注意しましょう。スマホやラジオなどで随時最新情報を確認することも忘れずに。
⒌保護者への連絡と受け渡し
保護者の緊急連絡先が書いてあるファイルや緊急避難袋等は避難時に持ち出しましょう。(事務室で管理している場合、誰が持ち出すかを決めておくと安心です)
アプリやメールで一斉連絡をしたり、電話を入れたり、緊急時の受け渡しルールに則り保護者へ連絡をします。保護者の中にはすぐに連絡に出られない場合もあるでしょう。焦らず時間をおいて連絡を入れてみましょう。
受け渡し時には必ず記録を残しましょう。また、東日本大震災では子どもの受け渡し後に津波によって亡くなってしまった親子もいました。園に待機したほうが安全な場合もあるため、慎重に判断しましょう。
⒍子どもたちに寄り添う
非常時には多くの子が不安を感じています。声に出して「怖い」と表現できない子もいるでしょう。お父さんやお母さんの心配をする子もいると思います。保育者は「大丈夫だよ」と声掛けをするだけでなく、できるだけ手を握ったり抱きしめたりスキンシップをすることで安心させてあげましょう。
発生場面ごとの対応のポイント

地震はいつ・どこで発生するか分かりません。保育室で工作をしているとき、給食を食べている時、散歩で園外に出かけているとき……さまざまなケースが想定されます。
室内で活動していたとき、屋内で活動していたときをそれぞれ想定し、注意点をまとめました。
室内で活動中
- 窓を開けて避難経路を確保する
- 子どもたちを落下物の少ない場所に集める机の下やマットの下に誘導する
- トイレにいる子を安全な場所に誘導する
- 給食室で火を使用している時間帯は火災に注意
- 余震が落ち着いてから屋外の安全な場所に避難する
屋外で活動中
- 落下物の少ない一箇所に子どもたちを集め、大人が囲む
- 地割れや倒壊した塀などには近づかない
- すべり台などの遊具に乗っている子を抱っこで下ろす
- 散歩中の場合は園にすぐ戻るのではなく、現状報告の電話を入れて余震が落ち着いてから帰る
その他にも、プールに入っている場合、遠足に出かけている場合など、臨機応変な判断と対応が迫られることもあるでしょう。できるだけ多くの場面を想定し、緊急時に備えることが大切です。
日頃の訓練や地域住民との協力が重要に
災害発生時は、園内の職員だけでなく近隣の地域の人々との協力も必要です。「もしも」に備え、地域の人々と合同で避難訓練をしている園もあります。
また、非常時には限られた人数の職員で最善を尽くす必要があります。日頃から定期的に訓練を行い、子どもを見守る担当、周囲の安全確認をする担当、保護者に連絡をする担当など役割分担を明確にし、職員同士が上手く連携をとることが大切です。
地震を想定して訓練を重ねておくことで、いざその時が来ても落ち着いて対応することができるでしょう。
(記事公開日 2017年04月27日)
(記事更新日 2024年04月18日)
関連
 |
佐藤愛美(さとうめぐみ)
保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。 保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。 |